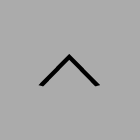COVID-19と漢方薬 続報
集中治療部の市山です。12月4日にYahooトップのニュースで報道されてから、「COVID-19に漢方が効く」や「COVID-19には葛根湯」というようにいわれるようになりました。
しかし、上記のコメントは正確ではなく、あくまで今回の論文で示されたのは、葛根湯 1回2.5g 1日3回と小柴胡湯加桔梗石膏 1回2.5g 1日3回を14日間内服した群が、標準的な症状緩和薬を使用された群と比べて成績が良かったという事のみです。
漢方礼賛, 葛根湯礼賛という姿勢は誤りであり、本来はその論文を批判的に読む姿勢が必要です。一般マスコミでは細かい事を書いても読者にはうけないので、わかりやすく伝えようとします。その際に若干ニュアンスが変わってくる事が往々にあります。それが口コミで他の人に伝わる際に、伝言ゲームみたいに少しずつニュアンスが変わってくるという事も起こりえます。
今回のコラムは、まず今回報告された論文の内容を詳しく紹介したいと思います。
Front Pharmacol. 2022 Nov 9;13:1008946. doi: 10.3389/fphar.2022.1008946. eCollection 2022.
「Multicenter, randomized controlled trial of traditional Japanese medicine, kakkonto with shosaikotokakikyosekko, for mild and moderate coronavirus disease patients」
日本語訳:軽度および中等度のコロナウイルス感染症患者に対する和漢薬「葛根湯」と「小柴胡湯加桔梗石膏」による多施設共同無作為化比較試験
1例目の登録日 2021年2月22日,
最終経過観察日 2022年2月16日
軽症、中等症のCOVID-19患者161名を1:1にランダムにわけて治療を行う。
それぞれの群に何の薬が使われているかは分かる(二重盲検ではない)
両群とも抗ウィルス薬、抗体薬、ステロイドは使用していない。
標準治療群 80例
38℃以上の発熱 アセトアミノフェン 500mg 1日3回まで
咳の症状が2以上の場合 ジモメルファンリン酸塩 30mg/日
喀痰の症状が2以上の場合 カルボシステイン 750mg/日を使用
登録基準を満たさず1例離脱。病状悪化による介入継続困難で10例離脱。
症状消失のため1例離脱。
解析は79例、
試験開始日の症状スコアが記録されていなかった6例を除外
主要評価項目分析 73例
漢方群 81例
標準治療群で使用される症状緩和薬に加えて
葛根湯 1回2.5g 1日3回, 小柴胡湯加桔梗石膏 1回2.5g 1日3回 14日間内服
登録基準を満たさず1例離脱。病状悪化による介入継続困難で9例離脱。
解析は80例,
試験開始日の症状スコアが記録されていなかった10例を除外
主要評価項目分析 70例
主要評価項目
治療開始後14日以内に、発熱・咳・痰・息切れなど少なくとも1つの症状が緩和されること。
副次評価項目
重症呼吸不全への移行, 投与開始後14日間における発熱・咳・痰・倦怠感・息切れの緩和
結果
65歳以上の患者は2人のみ。
| 漢方治療群 (70名) | 対照群 (73名) | ||
|---|---|---|---|
| COVID-19初診時重症度 | 軽症 | 27名(38.6%) | 32名(43.8%) |
| 中等症 | 43名(61.4%) | 41名(56.2%) | |
| ワクチン接種 | 7名 (10.0%) | 7名 (9.6%) | |
| 使用薬剤 | 解熱剤 | 36名(51.4%) | 40名(54.8%) |
| 咳止め | 64名(91.4%) | 67名(91.8%) | |
| アレルギー薬 | 7名 (10.0%) | 10名(13.7%) | |
| 去痰剤 | 34名(48.6%) | 50名(68.5%) | |
| トランサミン(腫れ止め) | 6名 (8.6%) | 11名(15.1%) | |
| 気管支拡張薬 | 10名(14.3%) | 8名 (11.0%) | |
| 漢方群 | 標準治療群 | |
|---|---|---|
| 少なくとも1つの症状を 評価できた |
70 | 73 |
| 全部の症状を 評価できた |
7 | 7 |
| 発熱 | 28 | 26 |
| 咳 | 64 | 65 |
| 痰 | 41 | 45 |
| 疲労感 | 44 | 42 |
| 息切れ | 18 | 20 |
| 呼吸不全への進行 | 6 | 10 |
通常の比較
漢方薬投与群では対照群と比べて発熱の回復が比較的早かったが、有意差はなし。
咳・疲労・息切れの緩和については両群で有意差はなし。
原疾患の悪化による脱落を競合リスクとする。
年齢(45歳未満または45歳以上)、重症度(軽度または中等度Ⅰ期)、発症から登録までの期間(7日未満または7日以上)、ワクチン接種, 各症状の初診時の程度を調整共変量とした。
共変量調整累積罹患率解析の結果
(← 勉強不足でどのような解析法か詳しく解説できません)
発熱の回復は対照群と比べて有意に早い。(HR 1.76, p=0.0385)
年齢と解熱までの期間の関係が有意だった。(HR 2.56, p=0.0031)
咳・息切れの緩和については両群間で有意差はなし。
年齢とワクチン接種の共変量は症状緩和までの期間と有意に関連した。
←ワクチンは両群とも7例(約10%)しか接種していない。
呼吸不全への病勢進行
対照群 10例、漢方群 6例
漢方薬群の法が対照群よりリスクが低かったが、有意差はなし。
→ 高齢者が予想外に少なかったため、軽症者やワクチン接種を受けた患者は重症呼吸不全に以降したのは少なかったのでは
初診時にワクチン未接種かつ中等症Ⅰの患者に絞って評価すると
漢方薬群は3例、対照群は8例であった。
漢方薬群は半分以下であったが、有意差はなかった。
有害事象
漢方群で心窩部不快感 1例、痛風 1例、手湿疹 1例が認められた。
しかし、両群間で有意差はなし。
上記がこの論文で示された結果でした。
う~ん。報道のされ方ほど、劇的な効果ではないのではないのではないか・・・?。
但し、漢方薬群と対照群はほぼ同じ割合で同じように症状緩和の薬を使っている。症状緩和に差があまり無くても当然かもしれません。
統計処理は非常に難しいですが、各群の症例数を決める際に有意な差がつくにはこれぐらいの症例数が必要だろうという計算式があります。少なくとも一つの症状を比較する場合は、想定した症例数が集まっていますが、各症状にばらけると、かなり症例数が減っています。そのため、有意差がつかなかったと考える事ができます。
今回の結論です。(完全に私見です。)
この論文では葛根湯+小柴胡湯加桔梗石膏がCOVID-19の特効薬ということは言えないのではと考えます。しかし、解熱するのが早くなりそうです。
もともと、私自身が風邪には風邪薬より漢方という考えだったので、(ちなみに風邪に抗生物質(抗菌薬)は効きません。)これまで通り、治療選択肢の一つとして考えるのは良いのではないかと考えます。
COVID-19軽症者の様子を伝え聞くと、2~3日で症状が治まる人がいるので、漢方を使うにしても14日間漢方を飲む必要はないと思います。
臨床試験というのは非常に難しいものです。そこから論文を書いて掲載されるというのはすごいことです。他にも有望な漢方薬の候補はあると思います。もちろん、葛根湯のみ、小柴胡湯加桔梗石膏のみでもある程度効果があるかもしれません。
また、抗ウィルス薬やワクチンなどのCOVID-19予防・治療の論文もしっかり読み込んでみたほうが良いかもしれません。
以上、1本の論文を読み込んでみると、長いコラムになってしまいました。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
集中治療部 市山 崇史
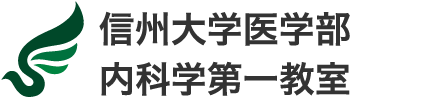 信州大学医学部附属病院
信州大学医学部附属病院